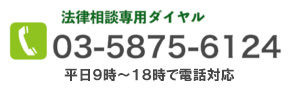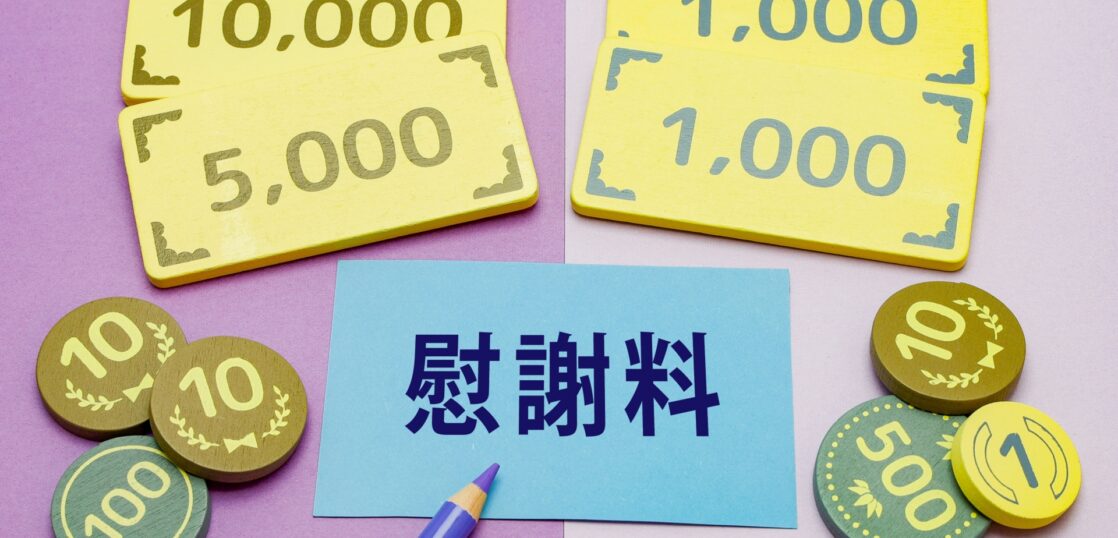離婚問題や不貞の問題に直面した際、「慰謝料はいくら請求できるのか」「誰に請求できるのか」といった悩みを抱える方は少なくありません。
この記事では、離婚慰謝料の相場、慰謝料の決まり方、さらに「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」の違い、そして「不真正連帯債務」の考え方までをわかりやすく解説します。
慰謝料請求の仕組みを知ることは、請求する側にとっても請求される側にとっても非常に重要なことですので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1 離婚慰謝料の相場はいくら?
2 慰謝料の金額の決まり方(考慮要素の一部)
⑴ 夫婦の結びつきの強さ
⑵ 夫婦の結びつきを断絶する行為の重大さ
⑶ 失ったものの大きさ
3 不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いとは
⑴ 不貞慰謝料
⑵ 離婚慰謝料
4 不真正連帯債務とは?不倫相手と配偶者の両方に請求できるの?
⑴ 不真正連帯債務とは?
⑵ ただし「二重取り」はできない
⑶ 慰謝料を支払った加害者は、他方の加害者に求償できる
5 不貞慰謝料と離婚慰謝料の二重請求はできるのか?
⑴ 二重請求は原則としてはできない
⑵ 複数の損害がある場合は別
6 当事務所の弁護士費用
7 まとめ
1 離婚慰謝料の相場はいくら?
一般的に、離婚時に請求できる慰謝料は50万円から300万円程度が目安とされています。
ただし、この金額はあくまで相場であり、実際の請求額は離婚に至るまでの事情や損害の大きさにより大きく異なります。
たとえば以下のような場合は、比較的高額になる傾向です。
• 不倫行為が長期間に及んだ
• DVなどによる身体的・精神的被害が大きい
• 婚姻期間が長く、夫婦間の結びつきが強かった
一方、精神的苦痛が軽度と判断された場合は、50万円~100万円程度となるケースも見られます。
2 慰謝料の金額の決まり方(考慮要素の一部)
慰謝料の金額は、精神的苦痛の対価であるため、一概に固定された基準はありません。そのため、請求側、請求される側の各種事情など諸事情を総合的に考慮して決定しますが、ひとつの判断尺度として、次のような観点も加味し、決定していくこととなります。
⑴ 夫婦の結びつきの強さ
婚姻期間が長い、未成年の子が複数いるなど、夫婦関係の結びつきが強いと、当然、離婚による精神的苦痛も一般的には大きくなる傾向があるといえるため、慰謝料額も増額方向に認定されやすい傾向はあります。
⑵ 夫婦の結びつきを断絶する行為の重大さ
離婚に至った相手方の行為の深刻さも重要です。具体的には、
• 性行為を伴う長期間にわたる不倫
• 不倫相手との間に子どもがいる
など重大な不貞行為であればあるほど、夫婦の結びつきの断絶の程度も大きくなると一般的にはいえ、それに比例して、精神的苦痛も大きくなるといえる傾向はあります。
⑶ 失ったものの大きさ
夫婦の結びつきを断絶する行為によって、完全に婚姻関係が終了(離婚)したのか、それとも別居止まりなのか、同居をしているものの夫婦関係は悪化したのかなど、失ったものの大きさも慰謝料額に影響します。
離婚が成立している事案は一般的には高額になりやすく、別居や関係悪化に留まる場合は状況に応じて金額が調整されます。
3 不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いとは
⑴ 不貞慰謝料
不貞慰謝料は、配偶者の不倫によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる慰謝料です。配偶者だけでなく、不倫相手にも請求できる点が特徴です。
さらに、離婚するかどうかに関係なく、不貞行為があった時点で請求が可能です。
⑵ 離婚慰謝料
離婚慰謝料は、離婚そのものがもたらした精神的苦痛に対する損害賠償です。
そのため、離婚に至った原因を作った「配偶者」にのみ請求することができます。
たとえ離婚の原因が不倫相手にも関係していたとしても、不倫相手に離婚慰謝料を請求することは原則できません。
もっとも、離婚した事案で不倫相手に慰謝料請求する場合は、当然、離婚したという事情を踏まえて慰謝料額を決定することになるため、金額は配偶者に請求する額とそん色ない額に通常はなります。また、後記4のとおり、不真正連帯債務という請求権の性質から、結果的には、配偶者にも不貞対手にも、全額を請求できることとなります。
4 不真正連帯債務とは?不倫相手と配偶者の両方に請求できるの?
不貞慰謝料は、配偶者と不倫の相手方の両名に共同で攻撃されて発生します。(共同不法行為(民法719条)といいます。)共同不法行為の加害者は、損害の賠償を連帯して行う必要があります。この連帯して賠償する義務のことを、「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」といいます。
⑴ 不真正連帯債務とは?
簡単にいうと、「複数の加害者に対して、それぞれに全額の支払いを求めることができる」という仕組みです。
不貞慰謝料の場合、配偶者と不倫相手は、共同で不貞という不法行為を行った加害者とみなされます。そのため、被害者はどちらに対しても「全額」の慰謝料を請求することが可能です。
たとえば、慰謝料が300万円と認められた場合:
• 配偶者に300万円を全額請求してもOK
• 不倫相手に300万円を全額請求してもOK
• 配偶者に100万円、不倫相手に200万円という形でもOK
どちらに、いくら支払わせるかは被害者が自由に選べます。
⑵ ただし「二重取り」はできない
ここで注意すべきは「同じ損害について、合計300万円を超えて受け取ることはできない」という点です。たとえば、配偶者から300万円を受け取った後に、不倫相手に追加で300万円請求することはできません。
これが「不真正連帯債務」の特徴です。複数の加害者に「全額」請求できるけれども、最終的に受け取る合計額は損害額の範囲内、というルールです。
⑶ 慰謝料を支払った加害者は、他方の加害者に求償できる
例えば、慰謝料を不倫相手が支払った場合、不倫相手は配偶者(または離婚した事案では元配偶者)に対して、求償請求できます。そのため、離婚はせずに不倫相手に慰謝料請求をした事案などでは、不倫相手から配偶者に対して求償請求がきてしまい、不倫をされた側と不倫をした配偶者の財布が一つ(家計が一つ)の場合などは、実質的に求償額を加味することで獲得額が半値程度に低減してしまうこともあります。
このような求償を阻止するために、求償権放棄の条項を和解のタイミングで入れる場合もあります。
5 不貞慰謝料と離婚慰謝料の二重請求はできるのか?
⑴ 二重請求は原則としてはできない
不貞慰謝料と離婚慰謝料は、法律上は別の種類の慰謝料ですが、同じ加害行為によって生じた精神的苦痛ですので、二重に受け取ることは原則できません。
たとえば、不貞行為が原因で離婚に至った場合、すでに不倫相手から不貞慰謝料300万円を受け取っている場合は、離婚慰謝料で同じ精神的苦痛について追加で配偶者に請求することは認められません。
⑵ 複数の損害がある場合は別
ただし、不貞行為に加えてDVやモラハラ、悪意の遺棄など、不貞の問題とは別の不法行為が存在する場合は、それぞれに対して個別に慰謝料が認められることもあります。
6 当事務所の弁護士費用
当事務所では、離婚をする事案のほか、離婚はせずに不倫相手に対してだけ慰謝料請求する事案も、いずれもお受けしております。ご依頼いただく場合の弁護士費用は次のとおりとなります。
https://kl-o.jp/divorce/#00002
7 まとめ
離婚慰謝料(配偶者を相手方とする)と不貞慰謝料(不倫相手を相手方とする)は請求相手が異なり、二重請求は原則として認められません。
また、不貞慰謝料の場合、配偶者が負う債務と不倫相手が負う債務は「不真正連帯債務」の関係にあり、被害者はどちらに対しても全額請求が可能です。ただし、配偶者と不倫相手のそれぞれからの二重取りはできず、求償権行使の可能性もあるため、正しい知識をもとに適切な請求を行うことが大切です。
慰謝料請求は、金額決定のプロセスが総合的な考慮を要するという点で簡単に額が決まらないという性質のほか、そもそも不倫相手や不倫をした配偶者を相手取って請求することから精神的にも辛い請求であることが多く、弁護士に委任することも十分あり得る類型です。
これらの問題について、少しでもお悩みの方は、まずはお気軽にお電話ください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124