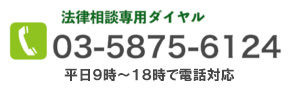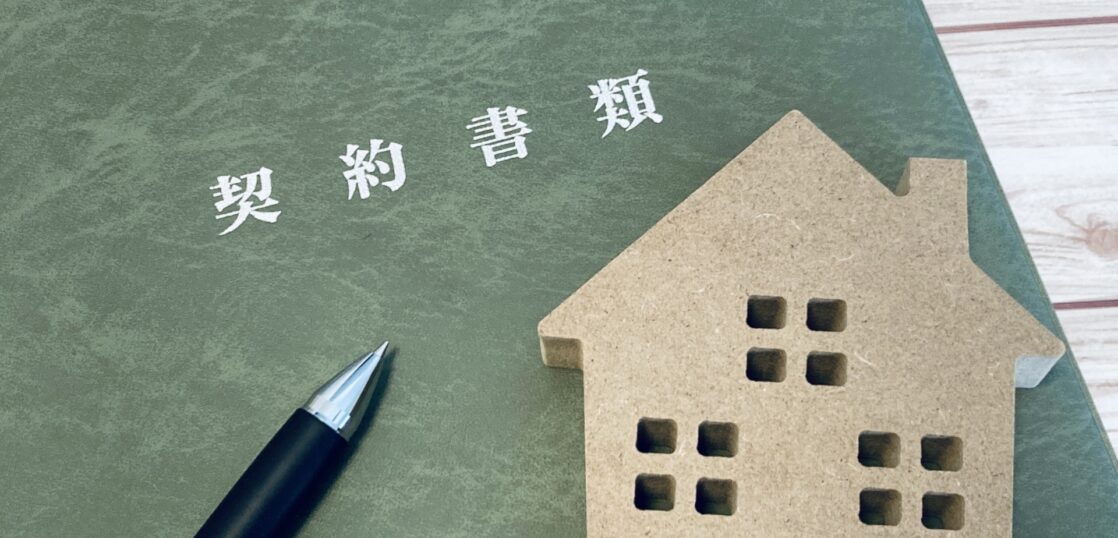「これって宅建業法違反じゃないの?」
「行政処分が絡むと、どう交渉は変わる?」
本コラムでは、そのようなお悩みや疑問をお持ちの方に、“民事×行政”という新たな視点から不動産取引・宅建業法を例に、民事紛争解決に行政法を活かす方法について解説いたします。
特に、宅建業者の方や不動産取引でトラブルに巻き込まれた方の解決のヒントになればと思います。
【目次】
1 民事法と行政法の交わり①~不動産取引を例に
2 民事法と行政法の交わり②~宅建業法違反が民法違反(不法行為等)になるか?
⑴ 宅建業法上の業務停止処分事由の例
⑵ 宅建業法違反と民法の関係─ネガティブ情報等検索サイトの活用
3 不動産問題・行政問題に関する当事務所の弁護士費用
4 まとめ
1 民事法と行政法の交わり①~不動産取引を例に
日本の法律は、民事法と行政法(と刑事法)に大きく分けることができます。
前者の民事法は、民法が典型例であり、民法では売買契約の成立要件、売買契約の効果等、私人と私人の権利義務関係が規定されています。
他方、後者の行政法は私人と行政機関(国、地方公共団体等)の法律関係(許認可・監督といった規制行政、補助金の交付といった給付行政等)を規定しており、本コラムで取り扱う宅建業法のほかに、例えば不動産に関わる行政法としては、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法などがあります。
このように、ひと口に「不動産取引」といっても、関係してくる法律は、民事法と行政法の二つの法領域に交わってくることになります。
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
(買主の追完請求権)
第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 (略)
(目的)
第1条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
(免許)
第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(略)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2~6 (略)
2 民事法と行政法の交わり②~宅建業法違反が民法違反(不法行為等)になるか?
⑴ 宅建業法上の業務停止処分事由の例
先ほど挙げた宅建業法では、宅地建物取引業の「適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図る」という目的(第1条)のため、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」(第65条第2項)という業務停止処分を規定しています。
そして、この業務停止処分事由としては、例えば以下の規定違反があります。
不動産の売買・賃貸借をしたことがある方であれば、特に⑤については「重要事項説明書」をご覧になったことがある方も多いかと思います。
②法第31条の3第3項(専任の宅地建物取引士の設置義務)
③法第32条(誇大広告の禁止)
④法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
⑤法第35条第1項~第3項(重要事項の説明等)
⑥法第47条第1号(故意による事実不告知・不実告知)
⑵ 宅建業法違反と民法の関係─ネガティブ情報等検索サイトの活用
宅建業法の業務停止処分事由は、あくまでも免許権者である都道府県等が、宅建業者に対して業務停止処分という「行政処分」をするかどうかに関するルールであり、宅建業者と取引をした私人との売買等の民事上の関係を直接の対象とするものではありませんので、宅建業者が「民事上の不法行為責任・契約責任を負うかどうか」は、あくまでも民法の不法行為責任・契約責任に関するルールに従って判断されることになります。
もっとも、不動産取引で問題となる説明義務違反のケースなどでは、裁判所も宅建業法第35条第1項~第3項の重要事項説明義務として挙げられている法令上の制限につき説明がなされているかどうかを重視することになるため、「宅建業法上どのようになっているか」という点を検討しておくことは、民事紛争を有利に解決するための重要な視点になります。
また、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」では、宅建業者等の行政処分歴を検索できるため取引の参考情報にできるほか、宅建業者として行政処分を受け、その事実が公表されることになると信用問題となるため、業務停止処分事由等に該当する事情があり得る不動産取引民事紛争では、(民事法と行政法の区別(後者が直ちに前者に結びつくものといえるかどうか)は意識する必要がありますが)宅建業者としても行政処分を回避するために損害を補填するインセンティブを持つことになりますので、必要に応じて宅建業法違反の点、過去の類似の処分事例を交渉においても指摘することが交渉戦略上有利に働く可能性があります。
3 不動産問題・行政問題に関する当事務所の弁護士費用
当事務所の弁護士費用の目安は、以下のリンクからご確認いただけます。
〇不動産問題
https://kl-o.jp/estate/#hudousanhiyou
〇行政問題(事業者、法人からのお問合せのみ受け付けております。)
https://kl-o.jp/gyosei/#00010
4 まとめ
本コラムでは、「重要事項説明」などでイメージが湧きやすい「不動産取引」「宅建業法」を例にとって、「民事紛争解決に行政法を活かす」という点につき解説しましたが、この点は事業規制法が制定されている取引一般にも応用することが可能なものです。
こういった行政法規違反が背景にあると思われる民事トラブルについて適切に指摘することで交渉が有利に運ぶケースもございます。何か少しでもお悩みの際は、当事務所でお力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料