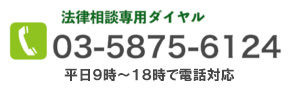本コラムでは、民事訴訟のIT化(デジタル化)について解説いたします。
【目次】
1 はじめに
2 改正法の段階的な施行-現在はフェーズ2
3 フェーズ3を踏まえた民事裁判手続の変革
4 当事務所の弁護士費用
5 おわりに
1 はじめに
近年、これまでの既存の情報通信技術にとどまらず、生成AI技術の革新・利活用が社会経済のあらゆる面で進んでおり、また、これらのAI技術を取り入れたリーガルサービスも数多くリリースされるなど、法律・司法制度も変革を迫られています。
このような社会経済情勢の大きな変化を踏まえ、時代に即して、民事訴訟をより迅速・適正なものとして、国民に利用し易いものとするという観点から、民事訴訟のIT化(デジタル化)が喫緊の政策課題とされていました。
このようなことから、令和4年5月25日、「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号)が公布されました。
2 改正法の段階的な施行-現在はフェーズ2
改正法は、IT化(デジタル化)の実現段階に応じて、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3の三つのフェーズに分けて段階的に施行・運用開始されており、いま現在はフェーズ2の段階まで来ています。
【フェーズ1】
• WEB会議(WEB裁判)による争点整理等(令和2年2月~)
• mintsによる裁判書類の電子提出(令和4年4月~)
【フェーズ2】
• 当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度(令和5年2月20日~)
• 当事者双方不出頭での弁論準備手続等(令和5年3月1日~)
• WEB会議による口頭弁論等(令和6年3月1日~)
【フェーズ3】
• インターネットによる申立て等(令和4年5月25日から4年以内)
• インターネットによる方法による裁判書類の送達(同上)
• 法定審理期間訴訟手続(同上)
• インターネットを利用した訴訟記録の閲覧等(同上)
3 フェーズ3を踏まえた民事裁判手続の変革
⑴ フェーズ3は、遅くとも令和8年5月25日までには開始することになります。
そして、フェーズ3の目玉である「インターネットによる申立て等」を導入するに際しては、最高裁判所主導で新たなシステム開発を進めるなどしており、これまでの書面提出(書面申立て)が原則であった民事訴訟につき、インターネットによる申立てが認められることとなります。特に、弁護士等の訴訟代理人が就いているケースにおいては、インターネットによる申立てが義務化されることになります。
また、法定審理期間訴訟手続は、日本の民事裁判手続には時間が掛かり、いつ解決するかの予測が困難で利用し辛いという国民の声に応えて創設された制度であり、一定の要件のもとで、訴訟開始から5か月以内に争点整理等を終え、6か月以内に口頭弁論を終結し、7か月以内に判決言渡しをするとされています。この法定審理期間訴訟手続は、あくまで当事者双方が利用に同意していることが前提となり、当事者から異議があれば通常の訴訟手続に移行するという建付けになっていることから(制度創設の際に、拙速な審理判断・ラフジャスティスになるという批判が多く寄せられたためです。)、果たしてどこまで利用されるかは未知数ではありますが、「法定審理期間訴訟手続」で生み出された適正迅速な審理判断のための手法は、通常の訴訟手続においても利活用される可能性を秘めています。
⑵ そして、いま現在、一部の裁判所では、このようなフェーズ3への移行(情報通信技術を積極的に活用した適正迅速な裁判の実現)に向けて、「データ活用型審理」、すなわち、準備書面・証拠資料等についてMicrosoft社のTeams上にアップロードした上でデータを整理・共有して審理の促進を図る、争点項目に沿った主張一覧表・証拠一覧表を作成して当事者双方の主張立証、裁判所の考え方などを一つのファイルに集約するといった実験的な試みが行われています。
また、法律雑誌等に裁判官が投稿する論文においても、民事裁判手続のIT化(デジタル化)を見据えて、これまでの審理運営・判決の在り方を見直すものが積極的に公表されるなど、あらためて民事裁判がこれからの時代に備えてどうあるべきかの議論が進んでいます。
⑶ このような裁判所の議論の流れを踏まえて、弁護士が作成する準備書面の在り方、証拠資料の在り方、訴訟戦略の在り方も大きな変化を迎える可能性がありますし、弁護士へのご依頼、特に民事裁判手続のご依頼を検討している相談者様においても、このようなフェーズ3への移行(情報通信技術を積極的に活用した適正迅速な裁判の実現)を踏まえて、弁護士のIT化・デジタル化への取り組み・新しい民事裁判手続への取り組みが一つの依頼の検討要素・考慮要素になるかもしれません。
4 当事務所の弁護士費用
当事務所では、以下のリンクのとおり、幅広い分野を取り扱っており、民事裁判手続のIT化(デジタル化)を見据えて、日ごろの執務にも積極的に情報通信技術を取り入れるなどの試みをしています。
特に、裁判日当については、遠方の事案などは看過できないほどに高額になるケースもあり、訴訟・調停ともにWEB裁判を積極活用することで依頼者様の負担軽減にも努めております。
弁護士費用
5 おわりに
本コラムで解説したとおり、フェーズ3を踏まえた民事裁判手続の変革が間近に迫っており、かつ、近時は裁判に持ち込まれる紛争も複雑高度になっていますので、民事裁判手続を利用する、民事裁判手続の利用を見据えて交渉を始める場合には、弁護士にお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124