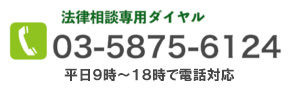「法定養育費制度が導入されると聞いた。」
「養育費の回収に関する制度改正があると聞いた。」
このようなご相談を受けることがございます。
本コラムでは、令和6年民法等改正(民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)による改正)のうち、養育費を巡る改正について解説いたします。
★ 家族法改正は、公布の日(令和6年5月24日)から2年以内の政令で定める日から施行される予定であり、本コラム執筆時点(令和7年6月4日時点)ではまだ施行されておりませんので、ご留意ください。
【目次】
1 養育費の不払いが広くみられる現状
2 養育費支払いの実効性確保のための令和6年民法等改正
3 離婚・男女問題に関する当事務所の弁護士費用
4 おわりに
1 養育費の不払いが広くみられる現状
父母(夫婦)が離婚をする場合の手続としては、
①協議離婚(離婚届の役所への提出)
②調停離婚(家庭裁判所における離婚調停による離婚)
③離婚訴訟(家庭裁判所における人事訴訟による離婚)
があり、9割弱程度は①の協議離婚により、離婚が成立しています。
この①の協議離婚に際しては、「子の監護に要する費用の分担」、すなわち「養育費」を定めることとされていますが(民法第766条第1項前段)、未成年の子の親権者を定めておけば、養育費を定めていなくても離婚届自体は受理されることなどから(ただし、法務省が作成している現行の離婚届様式には、養育費の取り決めをしているか否かのチェック欄が設けられており、これにより養育費の取り決めを事実上促してはいます。)、養育費の取り決めがなされていないケースが多くあります。
また、仮に離婚調停・離婚訴訟において家庭裁判所により養育費が定められた場合においても、支払義務者が支払わない場合には、裁判所に強制執行の申立てをしなければならず、回収のハードルは高いといえます。
このようなことから、厚生労働省の調査では、母子世帯で5割超、父子世帯で8割超の世帯が養育費の支払いを受けていないとされています。
2 養育費支払いの実効性確保のための令和6年民法等改正
養育費の取り決めがなく、支払いもないといった場合、母子家庭/父子家庭の別を問わず、ひとり親家庭の経済的貧困ひいては未成年の子の養育への悪影響に繋がる深刻な家庭問題・社会問題になります。
このような家庭問題・社会問題を民事法的に解決するために、以下の内容の令和6年民法等改正が行われ、公布の日(令和6年5月24日)から2年以内の政令で定める日から施行される予定です。
⑴ 法定養育費制度の導入
まず、養育費の取り決めをせずに協議離婚をした場合においても、養育費を請求することができるよう手当するために、法律上当然に毎月一定額の養育費を発生させる仕組みとして「法定養育費制度」が導入されることになりました(令和6年改正民法第766条の3)。
ア 法定養育費の要件
①養育費の取り決めをせずに協議離婚したこと
②父母の一方であって離婚時から引き続きその子の監護を主として行っていること
※ ただし、義務者が支払能力の欠如又は支払により生活が著しく窮迫することを証明したときはその全部又は一部の支払を拒むことができるとされています。
イ 法定養育費が発生する始期
離婚の日から
※ 従前の養育費については実務上、養育費を請求した時(養育費支払請求調停の申立て時等)が始期とされていますので、請求をしない以上は養育費が発生することは基本的にありませんでした。
ウ 法定養育費の支払いが終了する終期
以下のいずれか早い日まで
①養育費の取り決めをした日
②養育費分担審判が確定した日
③子が成年に達した日
エ 法定養育費の額
父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額
※ この法務省令は本コラム執筆時点(令和7年6月4日)ではまだ制定されていませんので、今後の動向を見守る必要があります。ただ、法務省令に対する委任の趣旨として「最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額」を考慮することが明記されており、父母双方の収入をいわゆる算定表にあてはめて計算される養育費と比較して低廉になることが予想されますし、養育費の現実的な支払いを確保する観点からも、法定養育費制度の導入後においても、協議離婚時等にきちんと養育費を取り決めておくべきことの重要性は変わりません。
⑵ 一般先取特権の付与
ア 養育費支払いの実効性確保のために、養育費の権利者(債権者)は、養育費の義務者(債務者)の総財産(典型的に想定されているのは義務者の給与債権)について一般先取特権(債務者のすべての財産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利)を有することとされ(令和6年改正民法第306条第3号)、これにより他の債権者に先立って養育費の優先弁済を受けられるようになります(同法第303条)。
イ また、一般先取特権に基づいて差押えをする場合には、養育費を定める審判書、調停調書といった家庭裁判所による債務名義がなくとも(≒裁判手続を経ていなくても)「一般先取特権の存在を証する文書」を提出すれば足りるとされており(民事執行法第181条第1項4号)、この文書は裁判所等を通さないいわゆる私文書でも良いと考えられています。
そして、この「私文書」のモデル案として、法務省が令和6年度委託事業として実施した調査研究の成果である「養育費請求のための民事執行手続に関する調査研究業務報告書」の別紙1に「モデル案(合意文書)」が掲載されているところです(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00369.html)。
ウ なお、養育費の一般先取特権は、「子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)」(令和6年改正民法第308条の2柱書)とされており、この法務省令は本コラム執筆時点(令和7年6月4日)ではまだ制定されていませんので、今後の動向を見守る必要があります。
⑶ ワンストップ執行手続の導入
従来は、民事執行法上の財産開示手続等で開示された給与につき、別途、給与債権の差押命令申立てをする必要がありましたが、令和6年民法等改正により、財産開示手続等で判明した給与債権の差押命令の申立てがなされたものとみなされることになり、財産開示→債権差押えがワンストップで行えるようになりました。
3 離婚・男女問題に関する当事務所の弁護士費用
離婚・男女問題に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://kl-o.jp/divorce/#00002
4 おわりに
令和6年法律第33号による家族法改正は、法定養育費制度の導入など、これまで解説したとおり家族法の重要な制度に関する大きな改正・見直しがなされるものであり、また、実際に施行されてからの法務省令の内容、裁判実務の動向(裁判所の解釈運用)にも目を配る必要があります。
離婚・男女問題でお困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124