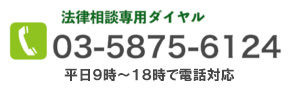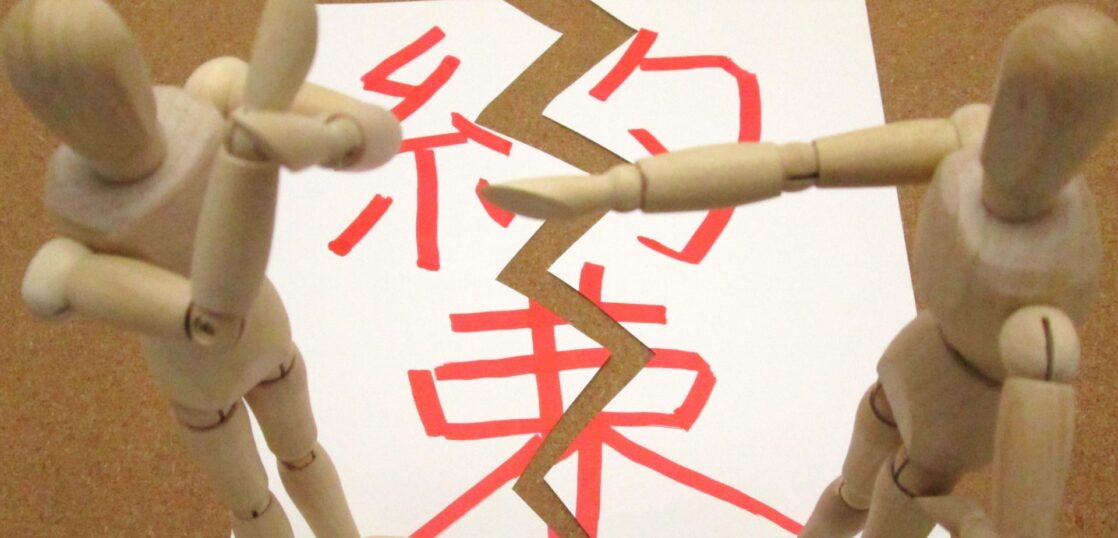「養育費について合意書面を作成したが支払われない。どのような手続をすれば良いか。一般的には養育費の問題は調停からと聞くので、調停を行うべきなのか。」
このようなご相談を受けることがございます。
本コラムでは、夫婦問題、相続問題の際の紛争解決手続選択の重要性について解説いたします。
【目次】
1 家事調停と民事訴訟の区別
2 婚姻費用・養育費を例にとって
3 離婚・男女問題に関する当事務所の弁護士費用
4 おわりに
1 家事調停と民事訴訟の区別
夫婦問題(親子問題)、相続問題といった紛争を解決するための手続として、以下の法的手続が用意されています。
①家事調停(家庭裁判所において調停委員が関与して行われる協議-家事事件手続法)
②民事訴訟(地方裁判所において裁判官が判決で権利関係を判断する訴訟-民事訴訟法)
そして、ひと口に夫婦問題(親子問題)、相続問題といっても、それらの紛争を解決するためには、これらの法的手続の中から最適なものを選択する必要があります。なぜならば、それぞれの法的手続ごとに解決できる問題に区別・限界があるからです。
そこで以下では、「婚姻費用・養育費」を例にとって、このことを解説いたします。
※人事訴訟(家庭裁判所において裁判官が判決で離婚等を判断する訴訟-人事訴訟法)もありますが、このコラムでは割愛します。
2 婚姻費用・養育費を例にとって
⑴ 婚姻費用・養育費につき、数は多くはないかもしれませんが別居・離婚時にインターネットの情報などを参考に、(公証役場で公証人が関与して作成する「公正証書」ではなく)当事者双方が署名押印したお手製の「合意書」(「離婚するまで毎月末日限り●万円を支払う。」など)を作成する場合があろうかと思います。
⑵ このような合意書がある場合において、相手方は支払いを怠るようになったときは、前記①の家事調停の申立て、または、前記②の民事訴訟の提起が考えられます。
この点、家庭裁判所の実務においては、養育費等について当事者の間に合意が成立している場合であっても、その合意を強制執行ができるような形にするために家事調停が申し立てられたときは、直ちに民事訴訟の提起を促すのではなく、その合意内容を踏まえて家事調停において解決するという運用がなされているところです。
ただし、あくまでも権利者が合意書による合意に基づく養育費の支払いを求める場合には、養育費の協議が調わない場合または協議ができない場合にすることとされている家事調停を申し立てることはできず、地方裁判所に民事訴訟を提起すべきであるとする裁判例(東京高等裁判所令和5年5月25日決定・判タ1522号118頁)もあるところです。
「合意書」があるようなケースでは、その合意書の作成経緯、合意内容(の明確性・確定性)、義務者が支払いを拒絶する事情等を踏まえて、紛争解決のための最適な手続を選択する必要があります(前記東京高裁決定では養育費支払請求審判の申立てが「却下」されているため、家事調停での解決は断念し、あらためて民事訴訟を提起せざるを得ないことになります。)
また、近時、最高裁判所では家事審判手続と民事訴訟手続との関係について重要な判決等がなされているため、このような判例の動向にも注意が必要です(→例えば、令和7年7月4日午後3時00分に最高裁の弁論が予定されている令和5年(受)第1838号 https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2025/jiangaiyou_06_239.pdf)。
3 離婚・男女問題に関する当事務所の弁護士費用
離婚・男女問題に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
なお、合意書がある事案において、強制執行できる形にするべく訴訟提起をする場合は、定形的な費用で対応できないケースもございますので、その際はお気軽に個別見積をお申し付けください。
https://kl-o.jp/divorce/#00002
4 おわりに
家族問題を適正に解決するためには、ご自身の主張立証の中身ももちろん大切ですが、どのような法的手続を選択するかということも同じように大切になります。
手続選択を誤ると、たとえば無意味な調停を提起して時間を浪費してしまう場合もあり得ます。
離婚・男女問題でお困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124