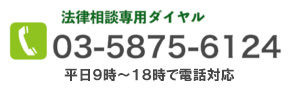「(敗訴した判決に基づき)所有している不動産が強制競売(強制執行)にかけられてしまったが、このまま不動産を失うと困るので何とか止めたい。」
このようなご相談を受けることがございます。
本コラムでは、不動産強制競売を止めるための手段について解説いたします。
【目次】
1 不動産強制競売の流れ
2 不動産強制競売の止め方
3 強制執行に関する当事務所の弁護士費用
4 おわりに
1 不動産強制競売の流れ
訴訟などの裁判手続の結果、「被告は原告に対し●●●万円及びこれに対する▲▲から支払済みに至るまで年■パーセントの割合による金員を支払え。」いった金銭の支払いを命ずる敗訴判決が確定し、例えば確定当時には手元に返済資金がないことからすぐに支払いが出来ない場合、勝訴した原告(債権者)が、敗訴した被告(債務者)の所有する不動産に対する強制競売の申立てをすることがあります。
この不動産強制競売は、おおむね以下のような流れで進みます。
(→次の法律コラムも参照ください。:「不動産強制競売手続の流れ」)
②債権者による予納金等の手続費用の予納
③裁判所による強制競売開始決定・差押登記
④執行官及び評価人による競売対象不動産の調査(物件明細書等の作成
⑤入札期間・開札期日・売却決定期日等の通知・公告
⑥開札期日(→買受の申出・執行官による最高価買受申出人の定め)
⑦売却許可決定(売却決定期日)
⑧買受人による代金納付・不動産取得(不動産所有権移転)
⑨配当期日
2 不動産強制競売の止め方
⑴ 何はともあれ弁済することが先決
ア 訴訟などの裁判手続で真剣に争った結果として敗訴判決が確定し、不動産強制競売の申立てにまで至っているケースでは、債務者が債権者に対して「(自宅)不動産を失うと困る。」と言ってみても債権者が不動産強制競売の申立てを取り下げるということは考え難く、基本的には不動産強制競売で債権者が回収しようと考えている金銭(請求権)を弁済することが何はともあれ先決になります。そこで、敗訴判決確定時には手元に返済資金がないことからすぐに支払いができなかった場合でも、金策をして返済資金を準備することが必要になります。
イ そして、この弁済に際しては、単に敗訴判決の主文に掲げられている元本(「被告は原告に対し●●●万円及びこれに対する▲▲から支払済みに至るまで年■パーセントの割合による金員を支払え。」の●●●万円の部分)の部分だけを支払うだけでは足りず、強制執行に要した「執行費用」等の「費用」、「遅延損害金」(「被告は原告に対し●●●万円及びこれに対する▲▲から支払済みに至るまで年■パーセントの割合による金員を支払え。」の「これに対する~金員」の部分)をも上乗せした金額を支払わなければ、債務の本旨に従った「本旨弁済」とはいえませんので、債権者に本旨弁済したい旨を申し入れ、本旨弁済をする支払期日を確定させ、支払うべき費用、遅延損害金、元本につき協議・合意した上で、現実に支払う必要があります。
また、債権者がこの協議などを拒絶して、弁済金を受け取らない場合には、ひとまず管轄の法務局に赴き「弁済供託」をすることになります。
このように、返済資金を準備できる算段がついた場合には、速やかに債権者に本旨弁済したい旨を申し入れ、本旨弁済に向けた協議を開始することが必要になります(債権者としては不動産強制競売が完了すれば配当を受けられ協力するインセンティブに乏しいことが多いので、この段階では債務者側から積極的にアクションをすることが必要になります。)。
⑵ 請求異議訴訟の提起等も必要(自動的に不動産強制競売停止にはならない)
加えて、前記2⑴イの債権者との協議を開始できたとしても、自動的に不動産強制競売が停止する訳ではありません。不動産強制競売自体は、裁判所の職権進行により粛々と進んでしまい、前記⑧の段階に至ると基本的には買受人に所有権が移転し、不動産を失うことになります。
そのため、不動産強制競売を止めたい債務者側としては、いま現在、不動産強制競売の手続が前記①~⑦までのどの段階にあるかを裁判記録の閲覧謄写などにより適切に把握して、請求異議訴訟の提起、請求異議訴訟の提起に係る強制執行停止の申立て、売却許可決定に対する執行抗告、執行停止文書の提出といった然るべき手続を債務者主導で行う必要があります(繰り返しになりますが、債権者としては不動産強制競売が完了すれば配当を受けられ協力するインセンティブに乏しいことが多いので、この段階では債務者側から積極的にアクションをすることが必要になります。)。
⑶ 債権者による取下げ・最高価買受申出人の取下げに対する同意の取付け
また、前記2⑴の債権者との協議、前記2⑵の請求異議訴訟の提起等を行ないつつ、債権者との間での本旨弁済に目途がつきそうであれば、最高価買受申出人に対し、不動産強制競売の取下げにつき同意してくれないかを持ち掛け、取下げによる解決を目指すという方向もあり得るところではあります(前記⑥の開札期日以降は、不動産強制競売の取下げが効力を生じるためには、最高価買受申出人等の同意が必要になります。)。
万が一、債権者及び最高価買受申出人の取り下げに対する同意が取り付けられない場合は、前記2⑵の請求異議訴訟及び強制執行停止において債務の本旨に従った弁済(又は弁済供託)を行った旨を主張立証し、請求異議・強制執行停止が認められるための訴訟等追行を行う必要があります。
3 強制執行に関する当事務所の弁護士費用
強制執行に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://kl-o.jp/debt/#saikenhiyou
※ 債務者側で強制執行の停止・取消等を目指す場合は、不動産強制競売手続の進行具合によるため、応相談となります(請求異議訴訟、強制執行停止申立て及び執行抗告を行う場合は着手金60万円~)。
4 おわりに
債務者側で既に申し立てられてしまった不動産強制競売を止めるためには、まず何よりも返済資金を用意することが不可欠になりますが、それだけでは用が足りず、不動産強制競売手続の進行具合に応じて、民事執行法上用意されている請求異議訴訟等の法的手続を然るべきタイミングで誤りなく、迅速に行うことが必要になります。
お困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料