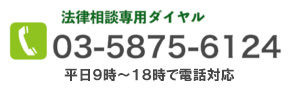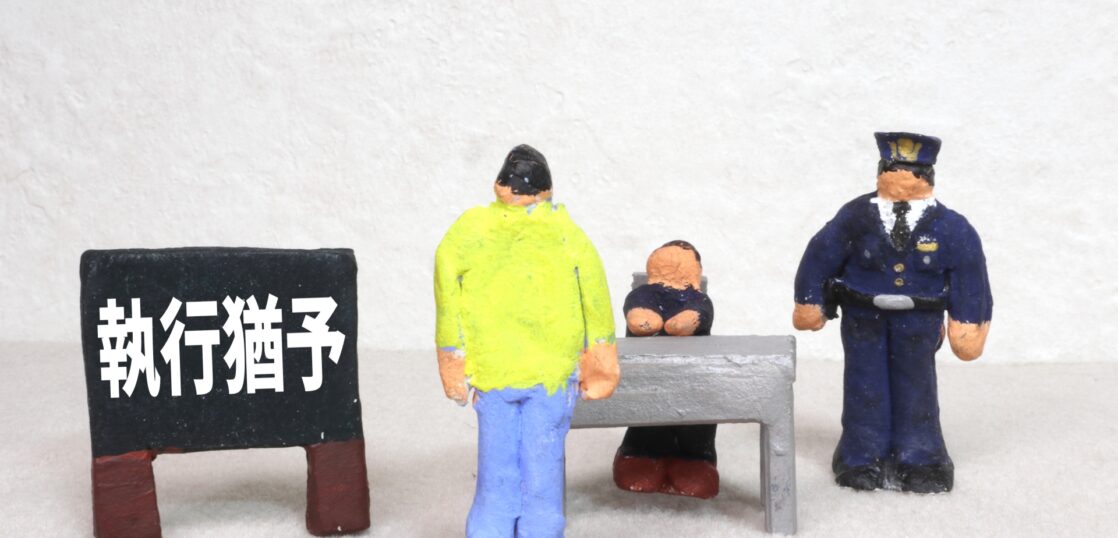令和4年に執行猶予制度に関する重要な法改正(刑法改正)がなされ、令和7年6月1日に施行されます。
このコラムでは、新しい執行猶予制度の内容と弁護活動に与える影響などについてご説明します。
【目次】
1 執行猶予制度とは
2 新しい執行猶予制度
3 新しい制度の中での弁護活動
4 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
5 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
1 執行猶予制度とは
⑴ 執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、執行猶予期間中に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度です。
例えば、裁判で懲役1年6月、3年間執行猶予の判決が言い渡された場合、この判決が確定しても直ちに刑務所に行く必要はなく、執行猶予期間である3年間、罪を犯さずに経過すれば、刑の言渡しは効力を失います。
⑵ 執行猶予の要件
執行猶予を付すための要件は、初度の執行猶予と再度の執行猶予とで異なります。
ア 初度の執行猶予
① 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者、又は、
② 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処されたことがない者が、
③ 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
④ 情状により、
執行猶予を付すことができるとされています(刑法第25条第1項)。
これを初度の執行猶予といいます。
今回の刑法の改正では、初度の執行猶予の要件に変更はありません。
イ 再度の執行猶予(現行法(改正前))
現行法上、
① 前に禁錮以上の刑に処せられその刑の全部の執行を猶予された者が
② 1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け
③ 情状に特に酌量すべきものがあるときは
執行猶予を付すことができるとされています(刑法第25条第2項)。
これを再度の執行猶予といいます。
なお、現行法上、保護観察付執行猶予中の者については、再度の執行猶予を付すことはできないとされています(刑法第25条第2項ただし書)。
今回の刑法の改正では、この再度の執行猶予の要件に変更がありました。
2 新しい執行猶予制度
⑴ 再度の執行猶予の要件の緩和
改正法では、再度の執行猶予の要件について
① 前に拘禁刑に処されたことがあってもその刑の執行を全部猶予された者が
② 2年以下の拘禁刑の言渡しを受け
③ 情状に特に酌量すべきものがあるときは
執行猶予を付すことができるとされました(改正刑法第25条第2項)。
改正前、再度の執行猶予を付すことができるケースは、1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける場合に限定されていましたが、今回の改正により、2年以下の拘禁刑(従前、懲役刑、禁錮刑とされていたものが、拘禁刑に一本化されました。)の言渡しを受ける場合にも執行猶予を付すことができることになり、再度の執行猶予を付すための要件が緩和されました。
⑵ 保護観察付執行猶予中の者に対する再度の執行猶予制度の創設
改正法では、保護観察付執行猶予に付され、その執行猶予期間中に罪を犯した者についても、再度の執行猶予を付すことができることになりました(改正刑法第25条第2項ただし書)。
なお、再度の執行猶予に保護観察が付されている場合において、その執行猶予期間中にさらに罪を犯した場合は、3度目の執行猶予を付すことはできないので注意が必要です。
3 新しい執行猶予制度の中での弁護活動
⑴ 執行猶予中の再犯の弁護活動
従前、執行猶予中に罪を犯した者については、弁護人において、「情状に特に酌量すべき事情」があることを立証し、再度の執行猶予を目指す弁護活動を行っていました。
しかし、事案の内容から、懲役又は禁錮1年を超える判決が見込まれる事案において執行猶予判決を得ることは困難でした。
この点、今回の改正によっても、「情状に特に酌量すべき事情」の立証が非常に重要であることに変わりはありません。
今回の改正による最大のメリットは、執行猶予中に罪を犯した者の刑期が1年を超える場合であっても、改善更生、再犯防止を図る観点から、実刑に処するよりも再度の保護観察付執行猶予を言い渡して社会内処遇を続けさせる方が適当であるとの主張を弁護人が正面からできるようになった点にあります。
例えば、窃盗を犯して執行猶予中の者が再犯に及ぶことなく真面目に生活していたところ、過失により交通死亡事故を起こしたものの、示談が成立し、遺族も寛大な処分を望んでいるような事案などにおいては、弁護人による適切な主張立証を行うことで、1年を超える刑期を言い渡しつつも、再度の刑の全部の執行猶予の判決が言い渡されることが十分に考えられます。
⑵ 保護観察付執行猶予中の再犯
従前、保護観察付執行猶予期間中の者が再犯に及んだ場合は、法律上、絶対に執行猶予が付くことはなく、弁護活動としては、(無罪や罰金相当の事案は別にして)、いかに実刑判決の刑期を短くするかという観点から情状立証に努めるしかありませんでした。
今回の改正により、保護観察付執行猶予の期間内に再犯に及ぶ事案には様々なものがあり、再犯に及んだというだけで社会内処遇によることがおよそ不適当であるとは言えず、実刑に処するよりも改めて保護観察付執行猶予を言い渡して社会内処遇を継続する方が罪を犯した者の改善更生、再犯防止に資するとの主張を弁護人が正面からできるようになりました。
例えば、窃盗罪で少年院送致の前歴を有しているなど、再犯のおそれが高いと考えられる若年者に対して、立ち直り支援のために保護観察付執行猶予が言い渡され、その後、真面目に生活していたものの、猶予の期間内に交通事犯を起こして公判請求された場合など、改善更生が図られている最中に偶発的に一種の犯罪に及んだと考えられる事案などにおいては、弁護人が適切な主張立証を行うことで、再度の保護観察付執行猶予を言い渡されることが十分に考えられます。
4 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
当事務所の刑事弁護に関する費用は次のページをご参照ください。
https://kl-o.jp/crime/#00003
5 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
これまで述べてきたとおり、再度の執行猶予を獲得するためには、弁護人が適切な情状立証をする必要があり、刑事事件に関する専門的知識やノウハウが豊富な弁護士の助言、協力が不可欠です。
当事務所は、元検察官の弁護士に加え、刑事裁判に関する豊富な知識、経験を有している弁護士が所属していますので、まずはお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124