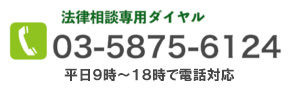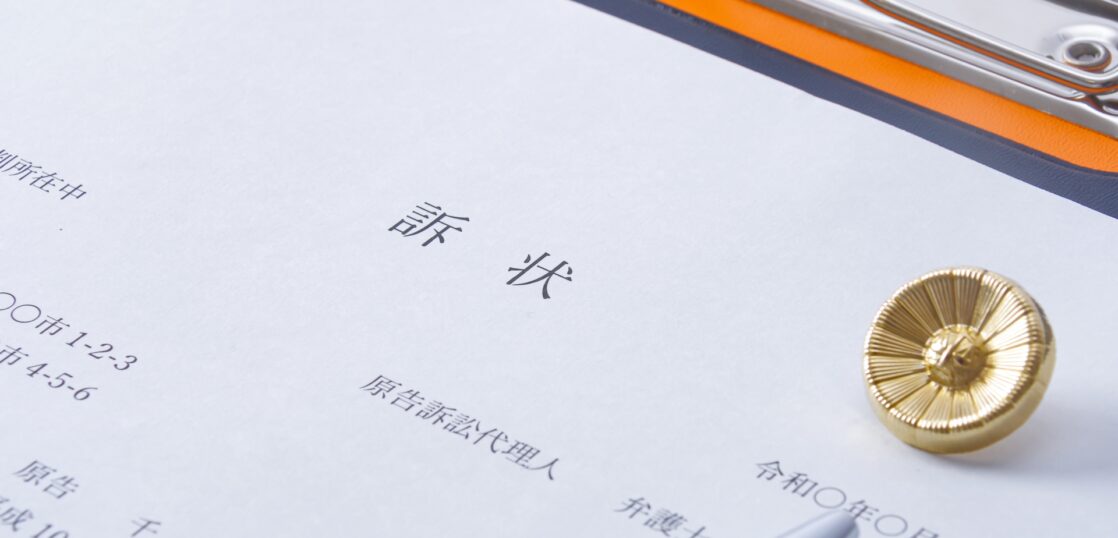「弁護士費用を相手方(被告)に負担させることはできるか?」
「訴状に『訴訟費用は被告の負担とする。』とあるが、敗訴した場合は弁護士費用も支払わなければならないか?」
このようなご相談を受けることがございます。
本コラムでは、弁護士費用を相手方に負担させることができるかについて解説いたします。
また、併せて訴訟費用額の確定手続についても解説いたします。
【目次】
1 弁護士費用の敗訴者負担制度が日本にはないこと
2 それでは訴状にある「訴訟費用は被告の負担とする。」とはどのような意味なのか?
3 その他のよくある疑問、利用できる手続
4 債権回収・強制執行に関する当事務所の弁護士費用
5 おわりに
1 弁護士費用の敗訴者負担制度が日本にはないこと
貸金返還請求訴訟、建物明渡請求訴訟、未払賃料請求訴訟などの訴訟提起をすることにより、権利を実現しようと考える場合、裁判手続には専門的な法的知識が必要になります。
日本では訴訟で弁護士を必ず付けなければならないとする弁護士強制主義が採用されてはいないものの、この観点から、弁護士にご依頼いただくことをまず考えられる方が多いかと思います。そして、この場合には、弁護士費用が掛かってくることになります。
そうすると、弁護士に依頼をして訴訟提起をすることを余儀なくされたのであるから、「弁護士費用を相手方(被告)に負担させることができないのか?」という疑問を抱かれる方がいらっしゃるのも当然かと思います。実際にこのようなご質問を受けることも多くあります。
しかしながら、日本では、弁護士費用を敗訴者に負担させる制度が基本的にはないため(限られた例外として、株主代表訴訟に関する会社法852条、住民訴訟に関する地方自治法第242条の2第12項などがある程度です。)、仮に勝訴したとしても弁護士費用を相手方(被告)に負担させることはできません。
判例上は、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟といった一部の類型で「弁護士費用相当額」を損害に計上するのが通例ですが、これも弁護士費用そのものではなく、「請求認容額の10%程度」が認められるに過ぎません。
2 それでは訴状にある「訴訟費用は被告の負担とする。」とはどのような意味なのか?
⑴ 他方で、原告として弁護士が作成した訴状を見たり、被告として裁判所から届いた訴状を見ると、「第1 請求の趣旨」といったタイトルのもとに、「訴訟費用は被告の負担とする。」と書かれているのを必ず目にするかと思います。
この「訴訟費用」とは、後述する「訴訟費用額の確定手続」を経て具体的に定まる、訴状に張り付けた印紙代等を意味するものであり、弁護士費用を意味するものではありません。
訴訟の結果、「訴訟費用は被告の負担とする。」とする主文が掲げられた認容判決を獲得できた場合でも、弁護士費用を被告に負担させることができるようになる訳ではありません。
⑵ そうすると、結局、「訴訟費用は被告の負担とする。」とは何なのか、という疑問が湧くかと思います。
これは要するに、訴訟費用被告負担の認容判決が確定した後に、第一審裁判所の裁判所の書記官に「訴訟費用額の確定手続」の申立てをした場合に限り、民事訴訟費用等に関する法律所定の以下の訴訟費用を被告に負担させる処分がなされるということになり、この処分に基づき訴訟費用を取り立てることができるようになる、という趣旨になります。つまり裏を返せば、訴訟費用額の確定手続をしなければ、判決主文で「訴訟費用は被告の負担とする。」と記載されても当然には被告に以下の訴訟費用を負担させることはできないということになります。
● 訴え提起手数料(印紙代) ※請求額によっては数十万以上になることもあります。
● 訴状副本等送達・送付費用
● 書類作成及び提出費用
● 期日出頭日当
● 期日出頭旅費
● 訴訟費用額確定処分送達費用
実務上は、民事訴訟費用等に関する法律所定の計算方法が煩雑である、別途弁護士費用を負担して訴訟費用額の確定手続を実施したうえで回収するような金額でもないなどの事情から、訴え提起手数料(印紙代)が高額になった場合を除き、あまり申立てはされていません。
3 その他のよくある疑問、利用できる手続
⑴ 「訴訟物の価額」というところに高額な金額が書かれていて不安
訴状には、「訴訟物の価額」という欄があります。
この訴訟物の価額は、訴え提起手数料(印紙代)を計算する際の基準金額であり、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟等では、訴訟物の価額と請求額が一致することもありますが、建物収去土地明渡請求訴訟等では請求額そのものではないため、ご自身がどのような請求をされているか(請求金額がいくらか)は、「請求の趣旨」という欄(「被告は、原告に対し●●●万円を支払え。」)を見る必要があります。
⑵ 代替執行費用支払申立て
その他、弁護士費用ではありませんが、民事執行法第171条第4項に基づき、建物収去土地明渡しに関する解体費用(建物収去費用)を債務者から債権者に支払うべきことを命じる「代替執行費用支払申立て」が用意されているなど、強制執行段階で利用できる特別な手続もありますので、そういった手続の利用を検討すべき場合もあります。
4 債権回収・強制執行に関する当事務所の弁護士費用
債権回収に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://kl-o.jp/debt/#saikenhiyou
強制執行に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://kl-o.jp/debt/#saikenhiyou
※ 債務者側で強制執行の停止・取消等を目指す場合は、不動産強制競売手続の進行具合によるため、応相談となります(請求異議訴訟、強制執行停止申立て及び執行抗告を行う場合は着手金60万円~)。
※ 訴訟費用額確定手続のご依頼は、事案にもよりますが、事件終了後に弁護士からご提案をさせていただくことになろうかと存じます。
5 おわりに
弁護士費用自体を回収することは難しいですが、訴訟費用額確定手続などの特別な手続が用意されていることもございます。お困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124