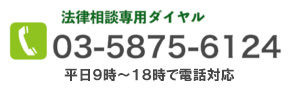「不動産の強制競売を検討しているが、不動産強制競売で売却価格は下がるのか?」
「不動産強制競売では普通の売買と違い、売却価格が下がると聞いたがなぜなのか?」
このようなご相談を受けることがございます。
本コラムでは、「不動産強制競売で売却価格は下がるのか?」について解説いたします。
【目次】
1 不動産強制競売のおおまかな流れ
2 評価人(不動産鑑定士)による評価とそれに基づく売却基準価額の決定
3 不動産強制競売特有の減価要因-競売市場修正(率)
4 競売市場修正(率)と買増率-不動産強制競売の落札額の実際
5 強制執行に関する当事務所の弁護士費用
6 おわりに
1 不動産強制競売のおおまかな流れ
金銭の支払いを命じる確定判決等に基づき申し立てることとなる不動産強制競売は、おおむね以下のような流れで進みます。
(→次の法律コラムも参照ください。:「不動産強制競売手続の流れ」)
②債権者による予納金等の手続費用の予納
③裁判所による強制競売開始決定・差押登記
④執行官及び評価人による競売対象不動産の調査、売却基準価額の決定
• 執行官 →現況調査報告書の作成
• 評価人(不動産鑑定士)→評価書の作成
• 裁判所書記官 →売却基準価額の決定
<以上の現況調査報告書、評価書、物件明細書を三点セットといいます>
• 執行裁判所 →売却基準価額の決定
⑤入札期間・開札期日・売却決定期日等の通知・公告
⑥開札期日(→買受の申出・執行官による最高価買受申出人の定め)
⑦売却許可決定(売却決定期日)
⑧買受人による代金納付・不動産取得(不動産所有権移転)
⑨配当期日
2 評価人(不動産鑑定士)による評価とそれに基づく売却基準価額の決定
不動産強制競売を担当する執行裁判所は、売却基準価額(不動産強制競売において不動産の売却の基準となるべき価額)を定める資料とするために、評価人(不動産鑑定士が選任されるのが一般です。)に対し、不動産の評価を命じます。
実務上は、評価人が執行官と日程調整をして同じ日に不動産調査に赴き、不動産に立ち入って所有者・占有者に質問したり、文書の提示を求めたりするなどして、調査を行います。その他、評価人は所管官庁から資料を取り付けるなどして、不動産に関する法的な規制を調査して、不動産評価を行うことになります。
この不動産評価の結果は、「評価書」という形で詳細に取りまとめられることになり、執行裁判所の閲覧室のほか、「BIT 不動産競売物件情報サイト」においても全国の競売物件の評価書(を含むいわゆる三点セット)をインターネットで見ることができます。
そして、執行裁判所は、この評価人の評価に基づき、売却基準価額を決定することになります。不動産強制競売において買受けの申出をする者は、この売却基準価額から20%を控除した価額以上でなければ買受けの申出をすることができませんので、債権者、債務者、買受人のいずれにとっても、この売却基準価額の決定は重要です(平成16年民事執行法改正前は文字通り「最低売却価額」という名称でした。)。
3 不動産強制競売特有の減価要因-競売市場修正(率)
このとおり売却基準価額の決定に当たり重要となる評価人による評価の仕方については、民事執行法第58条第2項に次の規定があります。
第58条 執行裁判所は、評価人を選任し、不動産の評価を命じなければならない。
2 評価人は、近傍同種の不動産の取引価格、不動産から生ずべき収益、不動産の原価その他の不動産の価格形成上の事情を適切に勘案して、遅滞なく、評価をしなければならない。この場合において、評価人は、強制競売の手続において不動産の売却を実施するための評価であることを考慮しなければならない。
3・4 (略)
上記太字の規定のとおり、民事執行法上の明文規定でもって、不動産強制競売特有の減価要因を考慮することが求められており、これを「競売市場修正(率)」といいます。要するに、不動産強制競売においては、不動産市場でなされる通常の売買契約と異なり、以下の事情があることから、この事情を考慮して減価をするということです。
• 差押債権者による申出がない限り、買受希望者が物件を直接内覧できないこと
• 所有者、占有者が居座るなどして引渡しが円滑に進まないおそれがあること
• 競争入札の方法によるため確実に買受けできる訳ではないこと
• 不動産の種類・品質に関する不適合については契約不適合責任がないこと
競売市場修正(率)は、個々の不動産の地域の需給バランスなどの個性に応じて評価人が考慮することから一概に言うことは難しいですが、「20%~40%減価される。」としている文献もあります。
4 競売市場修正(率)と買増率-不動産強制競売の落札額の実際
もっとも、不動産強制競売においては、競争入札の方法により、(買受可能価格以上の金額で)最高の落札価格を付けた最高価買受申出人が最終的に落札できることになるため、常に売却基準価額のとおりで落札されているという訳ではなく、売却基準価額と実際の落札額の間には開きがあることになります。この売却基準価額と落札額の割合を、「買増率」(かいましりつ)といい、都心部なのか地方部なのかなどに影響され一概に言うことは難しいですが、近時は140%~170%の間で推移しているとされています。
競売市場修正(率)と買増率を踏まえると、不動産強制競売の落札額の実際は、一例として次のようになります(競売市場修正(率)以外にも修正要素はありますが、分かりやすさの観点からここでは考えないことにします。)。
ある不動産
①不動産市場における一般の売買価格 …2000万円
②不動産強制競売における売却基準価額…1400万円(競売市場修正率30%)
③不動産競売における実際の落札額 …1960万円(買増率140%)
このように見てくると、不動産によっては、不動産強制競売においても競争原理が働いた結果、適正な価格での売却(落札)に至るケースもあるということになります。このような市場原理は、特に、都内で働く傾向にあります。
5 強制執行に関する当事務所の弁護士費用
強制執行に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://kl-o.jp/debt/#saikenhiyou
6 おわりに
不動強制競売、不動産仮差押えを検討する際には、実際には住宅ローン(抵当権)がある不動産も多いことから、抵当権者以外の方がこれらを検討する際には、オーバーローンの状態ではないかなどさまざまな事情を考慮して対象とする不動産を選定する必要があります。また、これまで説明したとおり、不動産によっては、不動産強制競売においても競争原理が働いた結果、適正な価格での売却(落札)に至るケースもあるということにはなりますが、その結果を予測することには困難な面があることも事実であり、民事執行法などの正確な法的知識を踏まえた適正・迅速な申立ての検討・判断が必要になります。
お困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124