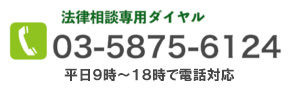「これから別居している夫/妻に対して離婚を求めるつもりだが、夫/妻名義の自宅不動産を勝手に売却されてしまわないか心配だ。」
「とにかく早く離婚がしたかったので協議離婚はしたものの、やはり財産分与を求めたいが、夫/妻名義の自宅不動産を勝手に売却されてしまわないか心配だ。」
このようなご相談を受けることがございます。本コラムでは、財産分与の対象となる自宅不動産を確保するために、離婚成立前・離婚成立後のそれぞれの状況に応じた仮差押えの保全処分について解説します。
【目次】
1.設例
2.離婚と同時に財産分与を請求する場合(協議離婚等成立前)の保全処分
3.離婚後(協議離婚等成立後)に財産分与を請求する場合の保全処分
4.離婚・男女問題に関する当事務所の弁護士費用
5.おわりに
1.設例
以下の夫婦共有財産(自宅不動産、預貯金)がある夫婦において、妻が夫に対して財産分与を求める場合を設例として想定します。
(夫婦共有財産)
・夫名義、住宅ローンも夫名義の自宅不動産(査定額3000万円、残ローン1500万円)
・夫の預貯金その他の夫名義の財産は不明
・妻の預貯金は300万円
(夫婦の状況)
・夫は上記自宅不動産に居住しているが、自宅不動産を売却するおそれがある
・妻は夫とは既に別居しており、上記自宅不動産ではない物件に居住
この設例では、夫が所有する自宅不動産について、査定額3000万円、住宅ローン残1500万円であるため、夫名義の純資産は1500万円(3000万円 – 1500万円)となります。また、妻の預貯金が300万円あります。そして、財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(夫婦共有財産)を2分の1ずつ公平に分けるものです。そのため、この自宅不動産の純資産1500万円と、妻の預貯金300万円を合算した1800万円が財産分与の対象と考えるのが原則です。
設例では夫の預貯金等の詳細は不明ですが、仮に夫と妻の財産を合算した共有財産が1800万円(夫名義の純資産1500万円+妻の預貯金300万円)と仮定すると、妻が夫から財産分与として受け取れる額は、1800万円×2分の1-300万円=600万円になります。
しかし、離婚協議中や離婚調停・離婚訴訟中に夫が自宅不動産を勝手に売却(換金)して、妻が把握していない預貯金口座に入金されてしまう、あるいは隠しやすい現金にされてしまうと、回収が現実的には難しくなってしまうおそれがあります。
そこで、回収の実効性を確保するために、以下の保全処分を検討すべき場合があります。
2.離婚と同時に財産分与を請求する場合(協議離婚等成立前)の保全処分
これから離婚調停、離婚訴訟をして離婚(請求)と同時に財産分与を請求する場合(協議離婚等成立前)には、「人事訴訟法上の保全処分としての仮差押え」(人事訴訟法第30条)を、離婚訴訟を提起する場合の家庭裁判所等に対して申し立てることになります。
この場合には、①離婚請求と財産分与請求が認容される蓋然性(具体的には、婚姻・別居の経緯、離婚原因の存在、夫婦共有財産の内容(→設例の場合は、夫名義の不動産・住宅ローンの内容、妻名義の預貯金の内容)、財産形成についての寄与度(→原則として2分の1))、及び、②保全の必要性(夫が自宅不動産を売却しようとしていることなど)につき、裁判官に一応確からしいと考えてもらう立証(疎明)をする必要があります。具体的には、離婚原因等についての陳述書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、不動産査定書、住宅ローンの残高証明書、預貯金通帳、不動産業者の広告・ウェブサイトなどを資料提出することになります。
なお、この場合、目的物である不動産の価格又は財産分与額(請求額)の最低10%程度の予納金を裁判所に納める必要があることに留意が必要です。設例の場合は、目的物である不動産の価格(ただし住宅ローンを控除したもの)を基準とすると、150万円程度が予納金になります。
3.離婚後(協議離婚等成立後)に財産分与を請求する場合の保全処分
離婚後(協議離婚等成立後)に財産分与を請求する場合は、「財産分与の審判事件を本案とする家事審判手続における審判前の保全処分としての仮差押え」(家事事件手続法第105条、第157条第1項第4号)を、財産分与の審判事件等が係属している家庭裁判所に対して申し立てることになります。
この場合は、①財産分与請求が認容される蓋然性(夫婦共有財産の内容(→設例の場合は、夫名義の不動産・住宅ローンの内容、妻名義の預貯金の内容)、財産形成についての寄与度(→原則として2分の1))、及び、②保全の必要性(夫が自宅不動産を売却しようとしていることなど)につき、裁判官に一応確からしいと考えてもらう立証(疎明)をする必要があります。具体的には、財産内容についての陳述書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、不動産査定書、住宅ローンの残高証明書、預貯金通帳、不動産業者の広告・ウェブサイトなどを資料提出することになります。
また、先ほどの2と同じく、この場合、目的物である不動産の価格又は財産分与額(請求額)の最低10%程度の予納金を裁判所に納める必要があることに留意が必要です。設例の場合は、目的物である不動産の価格(ただし住宅ローンを控除したもの)を基準とすると、150万円程度が予納金になります。
4.離婚・男女問題に関する当事務所の弁護士費用
離婚・男女問題に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://kl-o.jp/divorce/#00002
※今回の設例のように不動産に関する保全処分を要する場合は、個別の見積もりとなりますので、お気軽にご相談ください。
5.おわりに
財産分与の対象となる自宅不動産を保全するためには、手続のタイミング(離婚前か、離婚後か)に応じて、適切な法律に基づいた手続を選択する必要があります。
不動産の処分を心配されている場合は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124