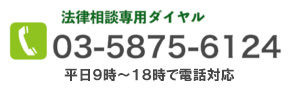ネット誹謗中傷で民事損害賠償を抑える――加害者側が知っておくべき実務ガイド
・インターネット(SNS、匿名掲示板など)で誹謗中傷をしてしまった。発信者情報開示請求を経て、自宅を特定され、弁護士から通知が届いた。どうしたら良いか分からない。
・自分の書き込みとの関係で開示請求をされ、損害賠償を請求されたが、金額として高すぎる。
・子供(または配偶者)が私の回線を使用して誹謗中傷をしていたようで、私が発信者情報開示請求を受け、開示されてしまっていた。
このような、いわゆる誹謗中傷等の「加害者側」とされる立場にまわってしまったことでお悩みの方は少なくありません。
もちろん誹謗中傷の内容にはよりますが、通常、実務上認定されるであろう相場を逸脱した相当に高額な請求と判断される事例も少なくはありません。
本記事では、損害賠償請求をされるまでの流れ、対応や弁護士に依頼するメリットについて解説します。
1 書き込みから損害賠償請求をされるまでの流れ
⑴ サイト管理者に対する発信者情報開示命令の申立て
⑵ 接続プロバイダの情報を得るための「提供命令」
⑶ プロバイダ名の提供(数日~数週間)
⑷ 接続プロバイダに対する発信者情報開示命令の申立て
⑸ ログ消去禁止命令
⑹ IPアドレス情報の提供と事件併合
⑺ 投稿者に対する意見聴取
⑻ 裁判所決定による住所・氏名の開示
⑼ 投稿者への開示通知
⑽ 代理人弁護士からの損害賠償請求
3 誹謗中傷の加害者側が弁護士に依頼する3つのメリット
⑴ 法的リスクの早期判断
⑵ 賠償額の減額を目指せる
⑶ 代理交渉・訴訟対応による負担減
4 弁護士費用
5 まとめ
1 書き込みから損害賠償請求をされるまでの流れ
⑴ サイト管理者に対する発信者情報開示命令の申立て
まず、書き込みをされた側は、掲示板や SNS を運営するサイト管理者を相手方として、IP アドレス等の発信者情報開示命令を申し立てます。
実名登録型サービスで電話番号・メールアドレス・氏名・住所をサイトが保有している場合は、これらの追加情報の開示も同一申立書で同時に求めます。
⑵ 接続プロバイダの情報を得るための「提供命令」
開示命令と併せて、サイト管理者に対し「接続プロバイダを特定できる情報を提供してほしい」という提供命令も申し立てます。1通の申立書で兼ねられるため、手数料は変わりません。
⑶ プロバイダ名の提供(数日~数週間)
提供命令は書面審理のみで迅速に発令され、サイト側には申立書と同時に決定書が届きます。これにより書き込まれた側は、投稿者側の接続プロバイダの名称・所在地を把握することになります(目安:1週間~2か月)。
⑷ 接続プロバイダに対する発信者情報開示命令の申立て
次の段階として、判明した接続プロバイダを相手に投稿者の住所・氏名等の開示命令を申し立てます。裁判所は先の事件と同一で、事件番号も引き継がれます。
⑸ ログ消去禁止命令
ログ保存期間が短いプロバイダについては、ログの消去禁止命令も同一申立書で併せて請求できます。実際にはプロバイダが任意保存することも多く、発令に至らない例も多いです。
⑹ IPアドレス情報の提供と事件併合
接続プロバイダ宛ての開示申立てを通知すると、サイト管理者は接続プロバイダへ IPアドレス等を提供します。サイトから裁判所への提供完了報告を契機に、第一次・第二次の事件は裁判所が職権で併合し、一体的に審理されます。
⑺ 投稿者に対する意見聴取
接続プロバイダ(場合によりサイト管理者)から投稿者へ、開示同意の有無や開示反対の理由を尋ねる意見照会が行われます(プロバイダ責任制限法6条第1項)。投稿者が同意すれば、裁判所決定を待たずに情報が開示されることもあります。この段階で、投稿者の方からご相談をいただくケースも多くございます。
⑻ 裁判所決定による住所・氏名等の開示
裁判所が開示を相当と判断した場合、接続プロバイダから申立人へ住所・氏名・連絡先が、サイト管理者からはIPアドレス・アカウント情報がそれぞれ開示されます。
⑼ 投稿者への開示通知
開示が実行されると、裁判所から投稿者へその旨の通知が発送されます。ここで初めて、自身の情報が開示された事実を確定的に把握することになります。この段階でご相談をいただくケースも多くございます。
⑽ 代理人弁護士からの損害賠償請求
以上を経て、発信者情報が開示された場合は、その情報に基づいて、通常は代理人弁護士から損害賠償請求の通知が届くこととなります。この段階で弁護士への委任を検討される方が最も多いです。
2 損害賠償請求の法的根拠と相場感
誹謗中傷を理由とする損害賠償請求(不法行為に基づく損害賠償請求 民法709条)は、その損害の内訳として慰謝料、調査費用、弁護士費用相当額(損害額の10%程度が目安)等を請求されるのが一般的です。
裁判例ベースの慰謝料相場は、その書き込み内容と書き込んだ対象者の性質等ケースバイケースとしか言いようがありませんが、ごく抽象的には一般個人への名誉毀損で 10~50万円、法人や事業者では 50~100万円がボリュームゾーンとされております。
もっとも、発信者情報は裁判所の手続を通じて開示されたものの、その後の訴訟では賠償額を0円と判断されることもあり、個別の事案に応じた、そのときの主張内容と証拠の状況によって慰謝料は決まります。
3 誹謗中傷の加害者側が弁護士に依頼する3つのメリット
⑴ 法的リスクの早期判断
いかなる書き込みのどのような点に問題があり、損害賠償請求がこのまま進行した場合どのようなリスクがあるのかをご説明できます。
具体的な数字は最終的には裁判官が決めることではありますが、過去の裁判例等に基づき、おおよそのボリュームゾーンは提示できる場合も少なくありません。
⑵ 賠償額の減額を目指せる
誹謗中傷の書き込みをし、発信者情報まで開示されると、裁判所の判断を既に経ていることから損害金を支払うことは避けられないと考える方も少なくないかと存じます。
もちろん、一定の損害をお支払いにならなければならない事案も多いですが、支払うべき金額を適正に保ち、事案によっては違法性がない書き込みであると反論すべき事案も少なくありません。
適正な賠償額に落ち着ける活動は本人のみによる対応では困難な場合も多く、弁護士を委任する最大のメリットといえるかもしれません。
⑶ 代理交渉・訴訟対応による負担減
誹謗中傷の事案で損害賠償請求がされる場合は、ほとんど、代理人弁護士を通じた請求かと思われます。 その場合、法的な知見が十分ではない書き込みを行った方ご本人が専門家である弁護士と交渉を行うことは精神的にも負担は大きいものと思われます。
さらに、訴訟対応となると、精神的にも技術的な点でもより負担は大きくなります。
そのような負担感やご不安感を弁護士に肩代わりさせるという点も弁護士を介入させる大きなメリットといえます。
4 弁護士費用
弁護士への依頼にあたっては、事案の内容や対応の範囲によって費用が異なります。
プロバイダからの任意開示への対応段階なのか、交渉段階なのか、訴訟段階なのか、などによっても費用が変わりますので、詳細は個別に確認いただくことが必要です。
誹謗中傷等の書き込みにより損害賠償請求を受けている側の当事務所の弁護士費用は、次のとおりです。
<着手金>
⑴ 協議(交渉):33万円
⑵ 訴訟:44万円
※協議(交渉)から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
<報酬金>※交渉・訴訟共通
⑴ 請求を減額した額300万円以下
請求を減額した額の22%(最低44万円)
⑵ 請求を減額した額300万円を超え3000万円以下
請求を減額した額の11%+33万円
⑶ 請求を減額した額3000万円を超え3億円以下
請求を減額した額の6.6%+165万円
⑷ 請求を減額した額3億円超え
請求を減額した額の4.4%に825万円を加えた額
5 まとめ
ネット社会といわれる昨今では、感情的になった一瞬の書き込みで「加害者」へ立場が転落しうる時代です。
しかし、適切な初動対応と法律専門家のサポートがあれば、高額な損害賠償請求でも現実的な水準に抑えることは可能です。
まずはお気軽にお電話ください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124